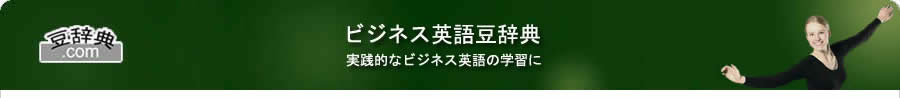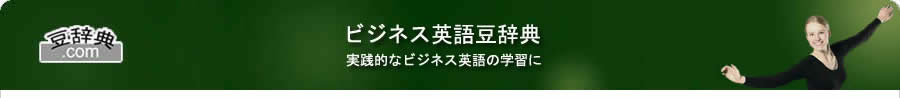| |
|
アメリカン・ビジネス
(連載エッセイ) |
 |
|
|
|
| |
アメリカン・ビジネス: 工場建設の話など、貴重な経験を紹介中。 |
|
7. 米国での工場建設 (ターンキー・プロジェクト) 第1話
A のアメリカにおけるビジネス経験の中で最も貴重な経験の一つが、ターンキー契約 (詳細後述)
で行った工場建設に係わる仕事だ。工場やプラントなどの設計から建設、そして、機械や設備の調達、据付、調整などをまとめて一括請け負う業者を英語では
Turnkey Contractor と言い、そした形式で行なわれるプロジェクトをターンキー・プロジェクトと言う。設計、土木・建設工事、配管や電気工事、機器調達・据付などを分離して発注する方法に比べ、スケジュールの短縮、責任の一元化、通常できない合理化とコストダウンが可能になるなどの利点があると言われている。加えて、ターンキー・ベースで発注すれば、通常不可能なプラントのパフォーマンスをギャランティーさせたり、設計が完全に終わっていないのに建設工事を始めることも出来るなど、オーナーにとってのメリットが多く、そうしたプロジェクトの割合は、年々、増えていた。
ある時、A もターンキーベースで受注したプロジェクトのマネジメントチームの一員として仕事をすることになった。親会社の顧客
(日本企業) が米国生産を計画していたのだが、日本にあるプラントのプロセス (process)、スペック
(specification)、そして、能力 (performance) をベースに米国工場を建設しようというもので、日本の親会社の営業が仕組んだプロジェクトだった。結果、A の勤めていた米国法人(子会社)
が、そのターンキー・プロジェクトを日本の顧客から現地工事などの業務を含めすべて一括請け負い、その一部を日本の親会社に発注するという契約形態で進めることになった。形式的には、エンジニアリング
(設計) の一部と主要機器を親会社に発注をするのだが、現地工事やプロジェクトの取り纏めの仕事も、親会社から米国子会社にプロジェクトのために派遣される日本人スタッフが米国現地のサブコン
(subcontractor) を使ってやる仕組みだ。この説明で、親会社がなぜ直接受注しないのかと疑問に思う方も居ると思うが、それには税務上の問題もさることながら、米国に既にある管理機能、人材やシステムを利用するためでもある。
 米国子会社の機能の一つは、こうしたプロジェクトが受注できた時にスムースにプロジェクトが遂行できるような受け皿の機能だ。つまり、プロジェクトを遂行するに必要な、人事、経理、総務、調査などの管理部門の機能は、米国子会社の機能が使え、プロジェクトを遂行する現場責任者やエンジニアだけが来れば、最低必要な機能は揃うという考え方に基づいた組織である。そんな体制と仕組みの中、米国法人は契約当事者になるわけだ。プロジェクトに必要な専門家は、その都度米国で雇うという考え方だが、子会社の立場からプロジェクトが間違いなく遂行されるかを管理するためには、子会社サイドの実務担当責任者が必要だった。そして、急遽、A がそのプロジェクト・ディレクターという役割を担うことになったわけだ。日本からの派遣者には、海外
(主に、中東など) でのプラント建設の経験のある百戦錬磨のプロジェクト・マネジャーも居たが、米国でのプロジェクトの経験のあるものはほとんど皆無だった。従って、A が実際にそうしたポジションにつくと 表面的な管理の仕事だけというわけには行かなかった。アメリカサイドに居るオーナーの代表者とのコミュニケーションから現地工事の取り纏めに係わる仕事まで、A があまり経験のない仕事でも、アメリカの商習慣や言葉が良く分かる A に日本から来るスタッフからの相談が次から次へと来るようになった。契約書
(英文) の作成には、深く関与していたから、契約の内容は、最初から熟知していたし、もともと工学部出身で、こうしたプラントで使う機械の市場調査やマーケティングの仕事の経験があった A には、生産プロセスや機器の基礎知識がそれなりにあったのだが、それでも経験のない仕事をしなければならないケースは山ほど出てきた。
> 続きは、こちら 米国子会社の機能の一つは、こうしたプロジェクトが受注できた時にスムースにプロジェクトが遂行できるような受け皿の機能だ。つまり、プロジェクトを遂行するに必要な、人事、経理、総務、調査などの管理部門の機能は、米国子会社の機能が使え、プロジェクトを遂行する現場責任者やエンジニアだけが来れば、最低必要な機能は揃うという考え方に基づいた組織である。そんな体制と仕組みの中、米国法人は契約当事者になるわけだ。プロジェクトに必要な専門家は、その都度米国で雇うという考え方だが、子会社の立場からプロジェクトが間違いなく遂行されるかを管理するためには、子会社サイドの実務担当責任者が必要だった。そして、急遽、A がそのプロジェクト・ディレクターという役割を担うことになったわけだ。日本からの派遣者には、海外
(主に、中東など) でのプラント建設の経験のある百戦錬磨のプロジェクト・マネジャーも居たが、米国でのプロジェクトの経験のあるものはほとんど皆無だった。従って、A が実際にそうしたポジションにつくと 表面的な管理の仕事だけというわけには行かなかった。アメリカサイドに居るオーナーの代表者とのコミュニケーションから現地工事の取り纏めに係わる仕事まで、A があまり経験のない仕事でも、アメリカの商習慣や言葉が良く分かる A に日本から来るスタッフからの相談が次から次へと来るようになった。契約書
(英文) の作成には、深く関与していたから、契約の内容は、最初から熟知していたし、もともと工学部出身で、こうしたプラントで使う機械の市場調査やマーケティングの仕事の経験があった A には、生産プロセスや機器の基礎知識がそれなりにあったのだが、それでも経験のない仕事をしなければならないケースは山ほど出てきた。
> 続きは、こちら |
|
 |
|
|