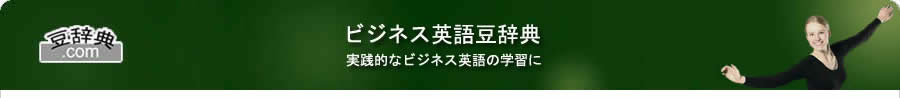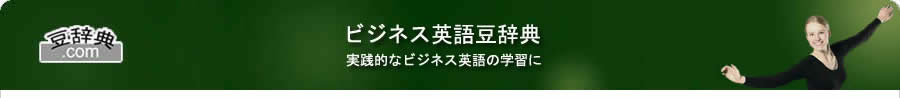| |
|
アメリカン・ビジネス
(連載エッセイ) |
 |
|
|
|
| |
アメリカン・ビジネス: 工場建設の話など、貴重な経験を紹介中。 |
|
6. 米巨大資本とのジョイントベンチャー 第2話
ジョイント・ベンチャー (J/V) は、何故か 50/50 という考え方が基本だったが、後に、ノンユニオンの工場にしたいという考え方から、日本がマジョリティーの
50.1% を所有するという計画になった。E社の組合との契約 (Master Contract
と言う) の対象となるのは、E社 が 50% 以上を所有する全てのオペレーションで、その条件から逃れるために そうした持分比率を双方が望んだという経緯だ。ただし、経営権は、双方が
50/50 で持つという基本概念で会社を設立する計画であった。
しかし、100万台生産する内、当初、日本側は 20万台しか販売できないから、そのフレームワーク
をどのように設定するか難しい問題だった。J/V で生産する製品を全て親会社である E社と A の会社とが買い取るということだから、外部
(Third Parties) に販売するのとは異なり、価格設定が微妙になった。つまり、買い取る製品の量が、50/50
であれば、どんな価格設定をしても、双方の投資利益率 (ROI - Return On Investment)
は同じになるが、80/20 の場合は販売価格が低くなればなるほど 80 を買い取る E社の利益が大きくなるのは明確だった。さらに、日本企業は資本以外に特許や生産技術など、ノウハウも提供するから、ライセンスフィーを取るという設定も必要だった。そして、その設定も、Third
Party を想定してフェアーと思われるレートにするという程、単純ではないバランス感覚というものがあった。また、E社は、日本企業にとっては馴染みのないパートナーシップ
(Partnership) という会社形態を提案してきた。パートナーシップは有限責任
(limited liability) の株式会社に対し、無限責任 (unlimited liability)
の組織になる一方、税務上のコストや利益の計上が親会社の一部という取り扱いで、損金の処理がすぐにでき、子会社のレベルでは課税されないなどという利点があるために提案されたものだった。いずれにしても、困難な話し合いになると思えた交渉も、何度かの話し合いを通じて 双方がフェアーと考えられる買取価格、ライセンスフィー、買い取り量増加のオプションの設定など、なんとか基本的な合意を見ることができた。
一方、そうした話し合いが順調に進んでいくと、どのような生産プロセス (設備、生産工程、品質管理など)
と組織および管理体制をとるべきかということを話し合うためにも、双方に相手の生産工場の見学をしようという話になった。A は、デトロイトでの打ち合わせの後、インディアにある
E社の当該部品生産工場を見学することになり、E社スタッフも、後日、日本へ工場見学に行くことで合意した。
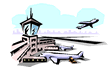 そんなことで、E社のスタッフと工場見学の日の朝に空港で待ち合わせたのだが、指定されたデトロイトの空港は、驚いたことに E社の自社用プライベート空港ターミナルだった。そして、そこからはアメリカ全土にある同社の工場への定期便
(それもボーイングのような機種のジェットが多い) が飛んでいた。ターミナルでは、発着便を示す電光掲示板があり、スケジュールを知らせるアナウンスなどが流れていて、まさにちょっとした地方都市の空港のような雰囲気と規模なのだ。また、ゲートからボーディング・ブリッジを通って、機内に乗り込むと、中は普通のジェット機のような座席の配置ではなく、打合ができるように考えられたテーブルと座席があり、スチュワーデスも搭乗していて、ドリンクなどが振舞われた。着いた先の空港は、普通の小さな町のローカル空港だったが
(こちらでは、タラップで乗り降りをし、粗末なターミナルしかない状況) 一民間会社がこんなに大きな空港ターミナルの運営と飛行機の運行までしていることには、日本からやってきたスタッフ一同全員、これがアメリカ巨大資本の姿かと大変驚いた事を、今でも鮮明に記憶している。 そんなことで、E社のスタッフと工場見学の日の朝に空港で待ち合わせたのだが、指定されたデトロイトの空港は、驚いたことに E社の自社用プライベート空港ターミナルだった。そして、そこからはアメリカ全土にある同社の工場への定期便
(それもボーイングのような機種のジェットが多い) が飛んでいた。ターミナルでは、発着便を示す電光掲示板があり、スケジュールを知らせるアナウンスなどが流れていて、まさにちょっとした地方都市の空港のような雰囲気と規模なのだ。また、ゲートからボーディング・ブリッジを通って、機内に乗り込むと、中は普通のジェット機のような座席の配置ではなく、打合ができるように考えられたテーブルと座席があり、スチュワーデスも搭乗していて、ドリンクなどが振舞われた。着いた先の空港は、普通の小さな町のローカル空港だったが
(こちらでは、タラップで乗り降りをし、粗末なターミナルしかない状況) 一民間会社がこんなに大きな空港ターミナルの運営と飛行機の運行までしていることには、日本からやってきたスタッフ一同全員、これがアメリカ巨大資本の姿かと大変驚いた事を、今でも鮮明に記憶している。
後日、E社スタッフは、日本に見学に行き、それに A もアメリカから同行したが、何と、1年以上こうした交渉や見学のアレンジなどをした挙句に、最終的に、このプロジェクトは壊れてしまったのである。それでも、結果的には、この経験が元で、A の会社は別のビッグスリーの
1社から受注をすることができ、工場を立ち上げることができた。このプロジェクトは、A にとっても、色々な意味で貴重な経験であった。> 続きは、こちら |
|
 |
|
|