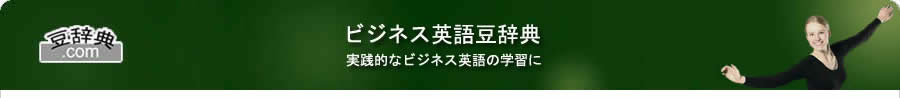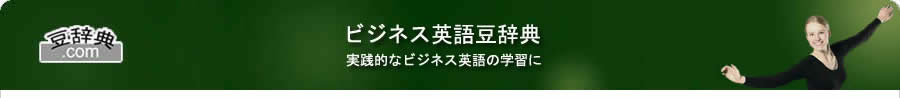| |
|
アメリカン・ビジネス
(連載エッセイ) |
 |
|
|
|
| |
アメリカン・ビジネス: 工場建設の話など、貴重な経験を紹介中。 |
|
5. 米巨大資本とのジョイントベンチャー 第1話
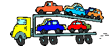 ご存知のとおり、1980年代になると日米経済摩擦が台頭し、輸出自主規制なるものが始まると同時に円高も急激に進行した。そうした状況を背景に、日本の自動車メーカーとその下請企業などが米国に進出して行ったわけだが、そんな中で、多くの企業が直面した大きな課題の一つは、採算の取れる最低の生産規模
(経済生産規模) をサポートできる販売能力の実現という問題だった。自動車メーカーは、その規模を年間
20万台としていたが、部品メーカーの経済生産規模は それよりも大きい場合が多く、自動車会社の
20万台の生産をサポートするために、いつ経済生産規模に達するか分からないような工場を建設するわけには行かないという問題があった。 ご存知のとおり、1980年代になると日米経済摩擦が台頭し、輸出自主規制なるものが始まると同時に円高も急激に進行した。そうした状況を背景に、日本の自動車メーカーとその下請企業などが米国に進出して行ったわけだが、そんな中で、多くの企業が直面した大きな課題の一つは、採算の取れる最低の生産規模
(経済生産規模) をサポートできる販売能力の実現という問題だった。自動車メーカーは、その規模を年間
20万台としていたが、部品メーカーの経済生産規模は それよりも大きい場合が多く、自動車会社の
20万台の生産をサポートするために、いつ経済生産規模に達するか分からないような工場を建設するわけには行かないという問題があった。
そうした中、日本の自動車部品メーカーは、どこもがビッグスリー (GM, Ford, Chrysler)
からの注文を取る事に努めていたが、そう簡単に受注できるはずもなく、当初は、最終工程の組立作業のみを米国で行うといったような比較的簡単なオペレーションを米国
(主に、中西部と西海岸) でスタートする企業が目立つ状況が見られた。一方、日本的マネジメントが注目を浴びる中、ビッグスリーは、失いつつある競争力を取り戻すために、日本企業との合弁事業
(Joint Venture) や各種提携に前向きに取り組む姿勢が見られるようになっていた。同時に、米国の自動車会社の部品の内製率が高いことも日本の自動車会社との違いで、それがコスト高の一因であるという認識もあって、部品調達のアウト・ソーシングや合弁子会社での生産などへの移行を積極的に検討するような風潮が広まって行った。
A もそうした大きな潮流の中で、ジョイント・ベンチャー (J/V) のプロジェクトチームのスタッフに選ばれ、ビッグスリーの一社
(仮名で E社) との交渉に深く関与するようになった。Aが務めていた会社には、E社にはない新しいタイプの製品を作ることのできる技術があり、その技術に
E社は大変興味を持っていたので、ジョイント・ベンチャーの提案をしたのだ。その製品の経済生産規模は、年間
100万個とされていたが、A の会社の販売能力では 年間 20万個の需要しか確保できない状況で、このジョイント・ベンチャーに活路を見出そうという考えだった。もともと、前述の工場用地選定調査の一つは、この製品を米国で生産するためのものだったのである。
さて、第一ラウンドの売込みが成功すると、第二ラウンドは 技術開示、サンプル提供の話に移る。そして、そのステップで必要になってくるのが守秘義務契約の締結だ。このサイトでも簡単な例をご紹介しているが、このレベルの守秘義務契約となると、お互いに相当細かい条件にも拘って、担当者レベルで簡単には合意できず、双方の弁護士が何度も口を挿むような展開になる。特に、ある種のコンフィデンシャル・インフォメーションの守秘義務の有効期限を相手は執拗に短縮しようとしていたのだ。
提供したサンプルは、耐久試験にかけられ評価される。耐久試験とは、比較的短時間の間に車が何万マイルも走行したのと同じような負荷をかけ、その耐久性を判定する試験のことだ。第1段階では、限られたサンプルの耐久試験、そして、それである程度満足の行く結果が出ると、次は数を増やし、統計学的に有意義なデータの収集へと作業が移るが、高価な耐久試験装置を何台も使うこの作業は、かなり時間と費用のかかるものだった。どのくらいの数の耐久装置が
E社にあったかは分からないが、A が見ただけでも社内にかなりの数の装置があった。それでも、装置は不足していたようで、どうしても試験期間を短縮するためには、外部の専門業者に耐久試験を依頼する必要があるような状況だった。そうした費用は、E社負担であったが、それにはかなりの費用がかかったはずだ。日本企業は、アメリカに居る人間だけでなく、日本からちょくちょく技術者がこの打ち合わせのためにデトロイトに出向いていたから、相当な費用がかかったことは言うまでもない。
一方、こうした段階まで製品と技術の評価が進むと、合弁事業のフレームワークの打合や製造プロセスの詳細なレビュー、そして、コストダウンのアイデアやターゲット・コスト設定などの話し合いをする段階へと入って行く。100点程ある部品を、エンジニアを含む双方のチームの代表が 一つ一つ事細かにレビューして行く。材料の種類、調達先、加工設備や機器、加工プロセス、加工精度、加工サイクル、検査工程などを何人もの専門家が集まってレビューし、意見やアイデアを出し合うわけだから、時間のかかるプロセスだ。日本チームは
5名、E社は部品の種類によって人が入れ替わったりしたので、かなりの人間が 打合に参加した。
> 続きは、こちら |
|
 |
|
|